・お団(歓喜団)
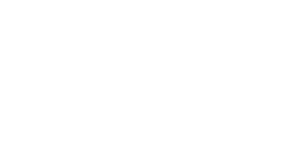

泉蔵院は真言宗智山派に属する寺院です。
弘法大師空海上人によって開かれた仏教(密教)の宗派です。
平安時代初期に弘法大師空海上人は中国より密教を伝え真言宗を立教開宗。
816年(弘仁7年)高野山を修禅の根本道場として開創しました。
823年(弘仁14年)嵯峨天皇より京都にある教王護国寺(東寺)を勅賜され鎮護国家の道場としました。
この両寺を中心に真言宗として教えを広めていきました。
平安時代後期、高野山の座主を務め、和歌山県にある根来寺を開いた興教大師覚鑁上人の教えの流れを新義真言宗といいます。さらに江戸時代の初め、新義真言宗の流れを汲む玄宥僧正により、根来寺の中にあった学頭寺院である智積院を京都東山の地に再興したのが智山派の興りです。

お寺の歴史は【縁起】あるいは【由緒】ともいいますが、当山は応長元年(西暦1311年)に示寂された宥阿上人の開創であり、また、永禄2年(1559年)に示寂された乗秀上人を中興開山として伝わっておりますので、平成23年(2011年)には、開創700年という記念すべき年を迎えました。
お寺には、一般的に山号・寺号・院号が付けられておりますが、当山は『御幣山阿弥陀寺泉蔵院』といいます。
明治20年(1887年)に編集された「地誌材料稿」には、
『毛長沼の辺りに昔からの万石長者が住んでいたが、ある時、天、突然として黒雲を起こし天地鳴動して長者の家宅・家族 全て悉く巻き上げられ、毛長沼に埋没してしまった。 後に残ったものは御幣1箇、阿弥陀如来1尊であった。村民はこれを見て昨日まで万石長者といわれしも、一朝の天災のために、かくも無惨な状態に至れりと痛く嘆き、長者の酒造蔵跡に一宇を創り残されたものを安置し、御幣山阿弥陀寺泉蔵院と名付け、長者の菩提を祈った』
と記されております。
また当山の近くに『毛長神社』という珍しい神社がありますが、この神社の由来についても、この「地誌材料稿」によると『長者が天災害を受けた後、毛長沼の岸辺に毛髪数尺なるものが漂い、村民がいかに流そうとしても流れないので、これは長者の娘の毛髪に違いないとして稲荷社に合祀し神社とした』と記されております。
これより考察すると、『泉蔵院』と『毛長神社』の開創は時を同じくしたものとみられ、御幣山の山号や阿弥陀寺の寺号の由来も明らかになってきます。
このように古い歴史と伝説を持つ寺でありますが、今日、泉蔵院は真言宗智山派に属し、御本尊は不動明王をお祀りしております。
また、他に類をみないといわれる【草加市指定有形民俗文化財】の「十三仏石像」「六地蔵尊」があり、史蹟と伝説を求めて多くの方が訪れております。

毎月1日~16日は、聖天尊御祈祷 を行っていますが、現在、新たな浴油祈祷は受付しておりません。お参りされたい方は寺務所で受付して下さい。
当山では、お申し込みによって車1台ずつのお加持・運転者の交通安全祈祷を行っております。お申し込みは早めにご連絡下さい。
※交通安全ステッカー・御守を授与致します。
地鎮式・上棟式或いは古家の取り壊し時のお祓い・方位除けなども行っており、随時受け付け致します。
厄年の厄除け祈願・七五三参りの身体健全・無事成長祈願など、お申し込みによって随時受け付けております。
後 厄 | 本 厄 | 前 厄 | |
|---|---|---|---|
男性の大厄42歳 | 昭和57年生 | 58年 | 59年 |
女性の小厄37歳 | 昭和62年 | 63年 | 64年・平成元年 |
女性の大厄33歳 | 平成 3年 | 4年 | 5年 |
男性25歳の厄年 | 平成11年 | 12年 | 13年 |
女性19歳の厄年 | 平成17年 | 18年 | 19年 |
幼児 4歳の厄年 | 令和 2年 | 令和 3年 | 令和 4年 |
男女61歳の厄年 | 昭和37年 | 38年 | 39年 |
13歳詣り・男女平成24年生まれ | |||
誰でも一回は訪れる最期の時を、厳粛に見送ることは人として大事なことです。
現在、直葬といって亡くなると病院から火葬場へ直行し、葬儀式を行わない風潮が見られますが、最後であればこそ縁のあった家族・親族はもちろんのこと、生前中お付き合いのあった者が集まり、お別れの気持ちを表し安らかな世界へ引導することは、至極当然のことかと思います。 華美ではなく心を込めた葬儀を。
当山では、弘法大師・空海上人より1200年伝わってきた引導法により亡くなられた方を仏として極楽浄土の世界へとお送り致します。
檀信徒以外の葬儀式も依頼により執行しております。
年回忌法要は毎回忘れずに行うことは大事なことです。
沢山の親戚を招かなくても、家族だけで行う法事でもよいのです。 或いはどうしても時間がとれなかったり、諸々のことで法事ができない場合は、卒塔婆を必ずあげてご供養下さい。 卒塔婆は亡き人に対する手紙です。年回忌の折には心を込めて卒塔婆をお建て下さい。
卒塔婆1本 : 4,000円
一周忌 | 令和 5年 |
|---|---|
三回忌 | 令和 4年 |
七回忌 | 平成30年 |
十三回忌 | 平成24年 |
十七回忌 | 平成20年 |
二十三回忌 | 平成14年 |
二十七回忌 | 平成10年 |
三十三回忌 | 平成 4年 |
三十七回忌 | 昭和63年 |
四十三回忌 | 昭和57年 |
四十七回忌 | 昭和53年 |
五十回忌 | 昭和50年 |
百回忌 | 大正14年 |

御本尊・不動明王
仏様は如来・菩薩・明王・天部に分けられますが、その明王部の中心たる仏が不動明王です。不動明王は大日如来の使者<教令輪身(きょうりょうりんじん)>の役目を負っています。すなわち、如来の教勅を受けて難化の衆生を救済しようという願いをもっています。その本体は大日如来そのものです。大磐石の上で火生三昧に住し、智慧の利剣をもって衆生を折伏し、慈悲の羂索(つな)で導いている姿、それが不動明王です。その恐ろしい顔、青黒色の身体は大きな怒りを表し、その怒りはそのまま衆生を救わんとする慈悲の極みを意味しています。
当山の御本尊・不動明王は江戸期の作とされ、矜羯羅(こんがら)・制吒迦(せいたか)のニ童子(眷属という)を従えた立像です。
地蔵菩薩
釈迦の入滅後、弥勒仏の出現するまでの間、無仏の世界に住して姿を比丘形(僧形)に現し、一切の衆生を教化救済すると願いをもたれている仏様です。また、地蔵菩薩は人々の苦しみをとり除き寿命を延すともいわれています。
当山の地蔵菩薩は立像で、本堂左側に安置され、衣は朱色に染められており、穏やかなお姿をしています。
阿弥陀如来三尊仏
中央に阿弥陀如来、左右に勢至菩薩・観世音菩薩の脇侍を従えた三尊仏立像です。
薬師三尊仏
東方浄瑠璃世界の教主であり、十二の大願をたて、病苦などに苦しむ衆生を救わんとされている仏様です。右手に施無畏の印を結び、左手に薬壺を持ち、日光・月光両菩薩を脇侍としています。
当山の薬師三尊は、平成18年に新しく造仏した仏様です。平成22年に本堂右側にお祀りしました。
毘沙門天(多聞天)
四天王(多聞天)、七福神の一人であり、仏法の守護神、北方を守る仏様です。右手に宝棒・左手に宝塔を持っています。
聖天尊
正しくは「大聖歓喜天尊」と申し、大日如来が「最後の方便」として、この世に出現せられた お姿であります。元々は毘那夜迦といい、大自在天の軍の大将で人々に障難(災い)をなす魔王であったが、十一面観音のお力により仏教に入り、福徳の神・仏法守護の神となったのです。一般的には毘那夜迦(男天)と十一面観音の化身(女天)が抱擁しているお姿、双身像が多く見られ、当山の聖天さまも双身のお姿をしております。
しかし、聖天さまのお姿は一般の者は見ることができず秘仏とされ、直接、頑拝できるのは住職が「浴油供」を修する時のみであります。その代わりに、聖天さまの本地仏である十一面観音さまを拝していただくのです。
ご縁日 : 毎月1日、16日
ご真言 : オン キリク ギャクウン ソワカ
十一面観世音菩薩
元々、当山の十一面観音さまは白檀で作られた総丈1尺ほどの小さな仏さまでありましたが、平成23年5月に聖天さまのお前立として新たに大きく作られ、信者さまが外陣より拝することができるようにしたものであります。
ご真言 : オン マカキャロニキャソワカ
軍茶利明王
宝生如来の化身ともいわれ、阿修羅や夜叉などの外敵から人々を守り、様々な障害を取り除くとされています。語源は「とぐろを巻いた蛇」、「甘露(不死の霊薬を入れる壺」という2つの意味があります。蛇は煩悩の象徴であり執念深さを表すとされ、軍荼利明王が煩悩をこれ以上ないというほど打ち砕くという意味です。
ご真言 : オン アミリティ ウン ハッタ
<聖天信仰とは>
聖天さまは数多い天部の神様の中でも、衆生(一般の私たち)を救わんとする摂取不捨(どんな者でも見捨てないで救わずにはおかない)のご威徳が強く勝れておりますので、どんな願い事でも叶えさせてくれる神さまです。
よって、聖天さまを信仰しようとする者は、その偉大なお力を理屈抜きに信じて、ただひたすらにお縋(すが)りすることが肝要です。
どんな願いでもよいが、うまず、たゆまず、永く信心していくことが大事であり、後の結果については聖天さまの思召(おぼしめし)として一切をお任せすることが最良の方法です。また、心願が叶った場合には聖天さまのご加護に感謝の念を忘れず、布施の心を持ち、広く社会の奉仕を心がけて行くことが必要であります。また、聖天さまは清浄を好みますので、穢(けが)れの場合には直接参拝することは、ご遠慮頂くこともあります。また、福徳の神でありますので、金品の出し惜しみは慎しまなければなりません。
住職も聖天さまへのご供養には、できる限り最高のものをお供えするようにしており、毎月のご祈祷には伽羅(きゃら)というお香を使用しております。このように、聖天さまは最強・最高の神であるが由に、種々の制約もありますが、その分、ご利益も他の仏さまでは得られない絶対的な施しが受けられるのです。ただ、ひたすら親神さまとして一心に信じ、お縋(すが)りする心、信じきる感謝と感激の心をあなたに。聖天さまはあなたが幸せな人生を歩まれるよう願って、いつもあなたを待っておられます。
合掌
十三仏石像
山門を入ってすぐ左側に、十三仏像が個々の形体で独立の立像として配列しています。入口より、不動明王(初七日の守り本尊)、釈迦如来(二七日の守り本尊)、文殊菩薩(三七日の守り本尊)、普賢菩薩(四七日の守り本尊)、地蔵菩薩(五七日の守り本尊)、弥勒菩薩(六七日の守り本尊)、薬師如来(七七日の守り本尊)、観音菩薩(百か日の守り本尊)、勢至菩薩(一周忌の守り本尊)、阿弥陀如来(三回忌の守り本尊)、 阿閦 (あしゅく)如来(七回忌の守り本尊)、大日如来(十三回忌の守り本尊)、虚空蔵菩薩(三十三回忌の守り本尊)の順に並んでいます。
いずれも高さ28センチ、 奥行き43センチの台上に立ち、左端の三個の台石の表面に造立の銘が刻まれています。「奉造立十三仏現当悉地成辨攸時千享六辛丑歳三月 日当寺第八世融宜願主西願敬白講中」これより享保六年(1721年)の造立ということがわかります。これらの像は、死者の追善供養のための石仏として建立されたもので、不動明王の初七日から始まって、虚空蔵菩薩の三十三回忌をもって終わりとなります。
当山の十三仏石像は他にあまり作例がないといわれている貴重な石像です。草加市指定文化財
六地蔵尊
地蔵菩薩は、釈迦如来の付託をうけて、六道界の衆性を化導するといわれています。
泉蔵院に所在する六地蔵は、六道別各尊名を刻してあります。元享釈書の惟高に依ったもので、右側より、地獄道=光味尊、餓鬼道=辨尼尊、畜生道=護讃尊、修羅道=不休息尊、人道=讃龍尊、天道=破勝獄尊とあります。地蔵の名称と容態を明らかに表現した造像として重要な意味を持つ石仏像です。この六地蔵は元禄四年(1661年)造立とされ、姿態は変わらず保存されているので貴重な史料となっています。草加市指定文化財
閻魔大王
平成25年11月、修復された閻魔大王は改築された閻魔堂において入仏開眼されました。地蔵菩薩の垂迹(すいじゃく)として、又、地獄の裁判官、或いは冥界(めいかい)の大先達とされるが我々の死後の平安を祈るよりも、現世の減罪生善の精神をもってお参りしたいものです。


「護摩(ごま)」という言葉は、古代インドの人々がバラモン聖典によって火の祭典を行い、その祭式を「ホーマ」と言った、その言葉の音写から由来しています。
しかし、私たちが現在行っている護摩は、真言密教の深い教えに基づいているものであります。
真言密教において、火は「真実の智慧・悟りの智慧」であり、これを智火といいます。大日如来の真実の智慧の火によって、私たちの迷いの心である煩悩(薪)を焼き尽くすのです。
人は何かを願い、祈る時は謙虚になります。自我・自己主張の強い現代、己を虚しくして省みて真の幸せを祈る。これこそが御本尊さまの願いではないでしょうか。
※護摩札は事前にお申し込み下さい。
小札 3,000円
中札 5,000円
大札 10,000円
◎11月の大護摩供には、「落語会」も併せて開催しています。
2023年(令和5年)
2022年(令和4年)
2021年(令和3年)
2019年(令和元年)
2013年(平成25年)
2012年(平成24年)
2011年(平成23年)

毎月(1日~16日)聖天堂において聖天祈祷を行っています。
聖天尊とは、正式に「大聖歓喜双身天王」といい、「凡そ人間の欲望には際限がないが、この欲望を満たし叶えることによって人を導こうとする」のがご誓願であります。
すなわち、「衣食足りて礼節を知る」という言葉があるように、まず現実に願いを叶えることによって本来の信仰の世界に導こうとしているのです。
この尊はお名前のとおり、天部の仏さまであります。天部の仏さまは人間に近い性格も併せ持っているため、全ての願いを叶えてくれる代わりに筋の通った信仰を求めます。
筋の通った信仰とは、一度信じたら決して疑いの念を持たない信仰です。ご利益がある・ないと言った軽い気持ちでお参りはできないのです。
しかし、心を決めて一心不乱にすがりつく時、絶対的なご利益を示してくれる仏さまです。
聖天様のお供物
仏飯・小豆粥・果物など、多くの御供物の中で、大根・お酒(和酒)・お団を何よりもお好みになるので、このお供物は日々のご供養に欠かせないものです。
・お団(歓喜団)
餡子(あんこ)の入った団子をゴマ油で揚げたもので、宝袋(きんちゃく)の形をしている。宝袋は財宝をいれるものですから、私たちに袋の中の福徳を与えてくださるという心を示されています。 ~増益(ぞうやく)【福を増す】~
・大根(蘿根・らふこん)
大根は滋養に富むと共に、貧(むさぼり)・瞋(いかり)・痴(ぐち)の三毒を消して頂けることを示されています。 ~息災(そくさい)【災いを除く】~
・お酒(和酒)
当山では、住職が本年で40年間聖天さまにご供養を続けており、毎月の縁日(1日・16日)には、商売繁盛・身体健全など諸々の願いを込めて信者さんがお参りをされています。また、平成22年6月には新しく聖天堂が完成し、新たな気持ちで精進供養していく所存です。お参りされたい方は寺務所までご連絡下さい。(但し、現在、新たな浴油祈祷は受付しておりません)

正式には「真言宗智山派密厳流遍照講」といいます。毎月の練習日には、講員さんの明るい笑い声が聞こえ、和気合々とした雰囲気の中、皆さん練習に励んでおります。また、年に何回かは奉詠大会、寺の行事などで大勢の人の前で奉詠しております。
興味のある方は遠慮なく寺までお問い合わせください。

毎年3月に春彼岸会法要を行っております。また平成22年からはコンサートも併せて開催しています。コンサートはどなたでも自由に聴くことが出来ますのでお気軽にご参加下さい。
2014年(平成26年)
2013年(平成25年)
2012年(平成24年)
2011年(平成23年)
2010年(平成22年)

毎年4月に、お釈迦様の誕生をお祝いし花まつり法要を厳修しております。法要の後、本堂前にお飾りしました花御堂にて法楽を捧げ、お釈迦様の誕生仏に甘茶をかけてお参りします。

毎年7月のお盆に草加聖地霊園の利用者を対象に開催しております。
お盆とは、『仏説盂蘭盆経』に由来するものであり、そもそもお釈迦さまのお弟子である目連尊者の母への孝養が元になっています。母への感謝、引いては親への恩、御先祖への感謝を表す機会として永く伝えられている行事です。また、「父母恩重経」という経典には「父母の恩は天に果てがないほど大きいものであり、孝養の心を持つならば、よく経典を写し、そして、7月15日に盂蘭盆の供養をしなさい。そうすれば仏の功徳を得て父母の恩に報いることができる」と説かれております。
2022年(令和4年)
2021年(令和3年)
2020年(令和2年)

毎年8月16日 午後2時より開催しています。
「大施餓鬼会」とは、お釈迦さまの弟子、阿難尊者がお釈迦さまから授かったといわれる施餓鬼法を修行する法会であり、迷いの世界に落ちているかもしれない多くの精霊を供養し、その功徳によってみ仏の世界に生きることができるように願う法要であります。毎年、法要には多くの檀家さんがお参りされ、それぞれのお墓にお塔婆をお供えします。
施餓鬼塔婆 1本 4,000円
お灯明料(志)
なお、当日参加出来ない方のお塔婆は翌日、お寺で各家のお墓にお供えしております。
2022年(令和4年)
2021年(令和3年)
2020年(令和2年)
2019年(令和元年)
2016年(平成28年)

皆さん彼岸と聞いて何を思い浮かべますか?
お墓参りやお仏壇の掃除、お花やぼたもちをお供えし、先祖や故人に線香を手向ける様子を思い浮かべるのではないでしょうか?
彼岸とは元々「到彼岸」を省略したもので、語源は「波羅蜜」(パーラミター)というサンスクリット語で、彼岸へ到達するという意味になります。煩わしさや悩みを脱した悟りの境地を「彼岸」(かなたの岸)といい、煩悩や迷いに満ちたこの世を「此岸(しがん)」(こちら側の岸)といいます。彼岸に到る為には善い行いを心がけ、悪い行いをしないようにし、自分自身の心を清めることによって到達できると説かれております。 お墓参りや仏壇における先祖供養も善行の1つですので、お彼岸期間中は是非家族そろってお墓参りをしましょう。

毎年12月31日 午後11時45分より除夜の鐘を行っております。
当山の除夜の鐘は、希望者から先着順に鐘を撞けます。「除夜」とは、日本の伝統的な行事であり、その夜は「1年の迷いを払い去る夜」という意味を持ちます。この特別な夜には、鐘が108回鳴らされ、その音と共に私たちの心の中に宿る煩悩や迷いを清め新たな年を心機一転迎えることができます。
2013年(平成25年)の除夜
2012年(平成24年)の除夜

荒井八重子さん
- 泉蔵院とのご縁をお聞かせください。
泉蔵院さんとは私が生まれる前からですので、相当古くからの、先祖代々ということではないかと思いますが、長くお付き合いさせていただいております。
現在のご住職さんは密蔵院からのご縁のある方で、とっても気さくで 奥さまともに何でも相談に乗っていただけます。いいご住職さんご一家に恵まれ檀家としては有難い事だと思っております。
- 泉蔵院は行事が多いと聞きましたが、いかがでしょう?
今年のお彼岸には尺八や民謡のコンサートもありました。毎年、色々な行事がありますが、こちらのお寺では特に宗派に拘るという事もなく、檀家の一人として、気軽に参加させていただいています。
- お寺の様子はいかがですか?
私も主人を亡くして30年になりますが、母の命日と合わせて毎月お花と線香をあげにきております。気軽にいつでもお墓詣りできるという感じで、檀家さんの皆さんや石屋さんも気さくに 声を懸けてくれますし、いつ来てもきれいに掃除されて、お墓の周りも草もなく枯れた花が 挿しっぱなしということもありません・・・・ほんとうに明るい素晴らしいお寺さんだなぁと思います。
- 境内はいつ来ても綺麗ですよね。
朝早くから、ご住職さん自ら箒をとられる姿には頭が下がります。若い副住職も立派だし、この先も泉蔵院が孫の代々此の儘続けてほしいと願っております。
- 世間では昨今、お寺離れしているとも言われていますが・・・
毎年、除夜の鐘が盛大に行われ、たくさんの参拝者が増えてきました。お寺さんに気軽に足が向いて、親密になってくる・・・ごく自然の大事な事ではないでしょうか。若い人の中には「お金がかかる」とか「お墓はいらない」という人もいるようですが、いざその立場になった時、お寺さんの有難さ、大事さが判って来ると思うのです。
- 最後に何かメッセージをお願いします。
夫や母を亡くした当時、ご住職さんの心のこもったお経の有難さは、30年経ってた今でも思い出しては有難く涙が出てまいります。泉蔵院さんとの御縁を一人でも多くの方が頂けたら有難いことだなぁと思います。
- ありがとうございました。